謎めいた題名(そして主人公の名前)
「あんがとな 浦野すず」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p15)
「モモヒキのすそに 書いてあった!」のは「すず」だけで、「浦野」は海苔の箱に大書されている。
- 「浦野すず」=「うら(裏)のすず」なので、実は「おもてのすず」がいるのである。
- というかこの「冬の記憶(9年1月)」に登場するすずが言わば「おもてのすず」で、それ以外の本編の主人公が「裏の」すずなのだ。
さて、それはどういうことなのか。
「あの日の事も きっと 昼間の夢だと 思うのだ」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p16)
題名は「冬の記憶(9年1月)」である。昼間でもなければ夢でもない。これは誰の記憶なのか?
(実際の出来事だとすると)些か妙な描写の数々
「あいつは 人さらい」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p11)
すずが落ちたという事は、籠には蓋もない訳だし、六神丸にされたのでもないのだから、周作も飛び降りるだけで逃げられる筈。
「どうなるん かねえ…」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p12)
ばけもんの背中の籠は伸縮自在なのか? どう見ても他のコマのそれより広過ぎる籠の中。
「ありゃ 何で寝と ってん?」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p13)
いくらなんでも、自分の頭をぶつけておいて気づかない訳がない。
「はい 確かに」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p16)
確認しているのに「のりが 1枚足りなくて」というのは不自然。
誰が、いつ語っているのか
「中島本町の 『ふたば』に 届けるのです」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p6)
リンのいた「二葉館」と同じ読みなのは偶然ではない。それにちなんで名付けられたから。
- つまりこの「冬の記憶(9年1月)」はこの物語(『この世界の片隅に』本編)の「後に」語られている。
「あのー すみません」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p9)
「第44回 人待ちの街(21年1月)」下巻p140)「ほいで もう 離れんで / ずっとそばに 居って下さい」と黒いボロの裾を引っ張った場面からの連想であろう。
- やはり21年1月より後に語られているのだ。
上段のコマで望遠鏡を覗くすず
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p10)
望遠鏡は、対物レンズ側のものを拡大して見せてくれるが、逆に接眼レンズ側のものは(対物レンズ側から覗けば)小さく見せるものだ(位置関係にもよるが)。
ばけもんの籠にそのままではすずと周作の2人は入らないが、
- 『山男の四月』で薬を飲まされた山男が四角い六神丸の包みの形に縮まったように
- この望遠鏡を覗いた者は縮むという仕掛け(この「冬の記憶(9年1月)」を語る上での設定)なのだろう。
それは、この話の語り手と聞き手の近くに望遠鏡があって、逆さまに覗いて遊んでいたりしたところからの連想かも知れない。
「小刀持っ とりん さる?」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p12)
次のコマで鞘が置かれているので、安価で普及していた肥後守ではない。周作の靴も上等そうだ。
「ええんじゃ / わしゃ また 買うてもらうし」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p14)
ばけもんにキャラメルを渡すのは『山男の四月』で「飴をくれない」という山男の呟きを意識してだろうか?
- 周作が無駄に格好いいのは、多分この話の語り手が周作だからなのだろう。
- そしてその場にすずはもう居ないのだろう。
- もし居るなら(下記のとおりの)周作によるこの全く事実と異なる作り話(あるいは周作が無駄に格好いいところ)にツッコミを入れずにはおれないだろうし。
つまりこれはすずが亡くなった後、(おそらくは孤児の少女に)思い出話を聞かせているのだ(まだ孤児の少女が望遠鏡を逆さまにのぞいて遊ぶような年頃に)。
- 思い出話と言っても
- 少年時代の体験と
- 「第44回 人待ちの街(21年1月)」での出来事
- をベースにした周作の創作話だが…
- (※孤児の少女にすずとの馴れ初めを聞かれて、人間違いだったとはさすがに言えないから)
- (そこにリンの思い出を紛れ込ませる周作の神経は理解しがたい…)
少年時代の周作が実際に体験した事は(描かれていないので)判らないが、本編との関係から推定すると「すずという名の少女と出会って」「ばけもんに似た誰かも居て」「海苔とキャラメルを媒介に何らかの交流があって」「そのまま別れた」といったところか。
すずが亡くなった理由も(描かれていないので)判らないが、
- すみの看病の為の広島通いの際、「第44回 人待ちの街(21年1月)」下巻p129)「汽車で 押された」り無理をしたりで
- 「第42回 晴れそめの径(20年11月)」下巻p115)「骨髄炎でも起こしたら また切らにゃいけんで…」と知多が懸念したとおりになった
のかもしれない(※抗生物質が日本で普及するのは戦後の昭和22年以降なので、恐らくその前に)。
「あの人 ばけもん じゃった?」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p15)
p11)「あいつは 人さらい」と言っていたのに
- (※攫われて状況が判らない筈なのに「人さらい」と断言するのも、話し手が周作だから)
ここでは「ばけもん」と言いだしたので、聞き手(孤児の少女)が(先ほどと設定が違うと)突っ込みを入れたのだろう。それが(おもてのすずに)反映されているコマ。
周作は「第44回 人待ちの街(21年1月)」でばけもんを見ている(というか雇っている)のでその外見を念頭にそう言ったのだが、孤児の少女は見ていないので。
- (そして、もしすずがその場に居れば周作の代わりに説明するだろうが、居ないので)。
「砂利が ちらばっ とろうが」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p6)
「砂利」は(丸刈りが普通だった時代、子供客の集まりを劇場の上から見下ろすと砂利のようにみえたことから)子供を指す隠語でもある。つまり、子供が、ちらばっている…
そして「本川を上がる船にすずが乗せてもらう」という点で呼応する「第44回 人待ちの街(21年1月)」下巻p133)で、船を降りたすずにかけられる言葉「おう そこ 足許に 気をつけえ の」の次のコマですずの足許にあるのは髑髏。死のイメージだ…
- 子供が、ちらばっている
- そして、死のイメージ
例えば
聞き手(孤児の少女)と語り手(周作)の他にも誰かが居て、すずの人生を振り返っている中で、亡くなったすずが右手を無くした時の状況、つまり
- 時限爆弾によって晴美の身体がバラバラに飛び散ったことと
- それをすずが目にしていること
それがすずにとって大変に辛い出来事であった(それこそ、砂利の上で正座するような)と、また別の誰かに語っているのが聞き手(孤児の少女)と語り手(周作)にも聞こえてきて、それが(おもてのすずに)反映されているコマ、なのかもしれない。
そして「じゃり」と言えば、『この世界の片隅に』の掲載誌である『漫画アクション』に掲載されていた『じゃりン子チエ』。その主人公チエは『この世界の片隅に』の作者と同じ、1968年生まれのようだ。
「モモヒキのすそに 書いてあった!」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p15)
「モモヒキ」と言えば、同じ作者の『百一』でモモヒキと共に81番目に登場するのが「ももしきや 古き軒端の しのぶにも 猶あまりある 昔なりけり」(順徳院)。
- 小倉百人一首では100番目の句であるが、詠み人の順徳院がそう呼ばれるようになるのは、選者とされる藤原定家の死後の事である。
- 定家が揮毫した色紙が小倉百人一首の由来とされているので、誰かが書き換えたという事になる。
この「冬の記憶(9年1月)」も、上記の通り、すずの死後に些か事実が書き換えられ、伝えられている。
右下のコマで20銭を眺めて妄想にひたるすず
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p7)
周作が実際に出会ったのだろう少女(本編を最後まで読むと、その少女は本編のすずとは別人だという事が理解できる。)のキャラメルに対するこだわりを予め仕込んでいるのだろう。
なお、森永ミルクチョコレートは10銭で大正8年発売。ミルクキャラメル(20粒入10銭)は大正3年発売。

ばけもんの言う「えらいこと」、そして読者にとって驚愕の「えらいこと」とは
「兄と妹におみやげを 買うて帰るのです……」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p6)
「わが家の晩ごはん となるのだ」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p11)
「わが家」ということは、ばけもんの他にも誰かが待っているということだろうか? ワニ嫁だとすれば、まず「第44回 人待ちの街(21年1月)」下巻p139)「鬼イチャン冒険記」が(恐らくすみの為に)語られて、その後その設定をベースにこの「冬の記憶(9年1月)」が語られているのだろう。
そして、この話「冬の記憶(9年1月)」が周作による全くの作り話と考えられる最も大きな理由、それは、昭和9年1月には、すずには兄も妹も居なかった、という事。
- つまり、以下で説明する(浦野家の)事情を誰も周作に教えなかったので
- 周作は当然、昭和9年1月当時もすずには兄も妹も居た筈、という前提でこの話「冬の記憶(9年1月)」を創作してしまった…
- さらに言えば、この話「冬の記憶(9年1月)」創作時点で、その(浦野家の)事情を知る人間は誰も居なくなっていたのかもしれない…
教科書の回(「第27回(20年3月)」)で触れたように、すずはサクラ読本の実物を見たことがない。この時(昭和9年1月)すみは小学1年で、しかもサクラ読本初年度で新品の教科書を持っているのだから、すずが興味を持たない筈がない。なのに見ていない。
加えて二人には経済的格差がかつてあった事にも「波のうさぎ(13年2月)」で触れた。経済的格差があるのだから恐らく全く別の家庭の筈で、つまり少なくともすずとすみはこの時(昭和9年1月)迄一緒に暮らしていない。色々な可能性があり得るが単純に考えれば、父の十郎と母のキセノは双方とも連れ子ありの再婚だったということだろう。
「第24回(20年2月)」で要一の合同慰霊祭に森田イトが参加している(が、浦野家側の親族は誰も居ない)ことから、要一は(森田イトと血のつながりがある、つまり)キセノの連れ子の可能性がある。
すずとすみはどちらかが十郎の連れ子だが、
- 「第1回(18年12月)」で、森田イトがすずに(教えて貰っていないのではと案じて)初夜の指南をしている。
- すずはタヌキ顔だが、すみもキセノも面長の美人。
- 「第6回(19年3月)」で、「もう六時半よ 急がんと!」とキセノが急かしている状況なのに、わざわざすみが「行って参ります」と出掛けるのを待ってから、「おこづかい 好きに使え」とすずに5円札を渡している。血のつながりのあるすずにお金を渡すところを、血のつながりのないすみには見られたくなかったのだろう。
- 「第33回(20年6月)」で、すずが、周作と径子が似ていることをとても気にしているのは、自分がすみのみならず要一とも似ていない(血がつながっていなければ当たり前だが)事との対比でそう思っていると考えられる。
といった事を考え合わせると、すずが十郎の連れ子なのかもしれない。そうすると、昭和9年1月には、すずには兄も妹も居なかった、ということになる。
- (「大潮の頃(10年8月)」で千鶴子が居ないのは、この事に気づかせようという仕掛け)
「夜がくる前に山へ 帰らんとえらいことに なるわい」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p11)
この話の時期とされる昭和9年1月、その月の8日22時頃、呉の海兵団に入団する新兵を京都駅から乗せる臨時列車を見送ろうと集まった群衆が押し合い転倒、77人が死亡、74人が負傷する惨事となった「京都駅跨線橋転倒事故」。まさに「えらいこと」だった。そしてp14)で夜になったと思ったのか、ばけもんもばったりと「転倒」している。
「父さんと汽車で 帰らんといけんのに」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p11)
周作の帰る汽車の行先はもちろん呉。「京都駅跨線橋転倒事故」の臨時列車の行先も呉。
また、呉に住む周作はこの事故の事をよく聞かされていただろうが、江波在住のすずはおそらくそれほどではないだろうというのも、この物語「冬の記憶(9年1月)」の語り手がすずよりも周作だろうと思わせる根拠の一つ。
荷物を背負わされているすずの背後の海苔干し台
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p5)
梯子の様な形の海苔干し台はこの後も「波のうさぎ(13年2月)」「第1回(18年12月)」「第36回(20年7月)」「第44回 人待ちの街(21年1月)」で登場するが、いずれも(2列)7段である。しかしこのコマだけは6段。
- このコマの海苔干し台がそもそも浦野家の所有物ではないかもしれないので、偶々この場所では6段の海苔干し台が使われていただけなのかもしれないが
- 江波や草津での海苔養殖を直接見た事がないのであろう周作が、この物語「冬の記憶(9年1月)」の語り手なのだとしたら
- 雑誌か何かで見かけた他地域の海苔干しの様子の知識をもとに
- 海苔干し台は6段だと語った(描写した)のかもしれない。
- つまりこのコマだけ6段なのも、この物語「冬の記憶(9年1月)」の語り手が誰なのかを示す為の手がかり、ということなのだろう。
地域によって違う海苔干し台の段数
昭和35年1月撮影とのことだが、下記リンク先で紹介されている海苔干しでは5段。
場所は全く違う(佐賀県)が、下記リンク先で紹介されている天日干しでは6段。
そして、浦野家のある江波は7段とのことである。
祝賀ムードではない理由
前年末の昭和8年12月23日に、昭和天皇、香淳皇后の第5子かつ初の皇子(第一皇男子)が誕生
しており、昭和9年1月8日の国内は祝賀ムードに包まれていた筈だが、「冬の記憶(9年1月)」に描かれる街の様子は祝賀ムードという感じではない。
上記の「京都駅跨線橋転倒事故」が祝賀ムードに実際にどの程度水をさしたのかは判らないが
- 周作にとっては遠い東京のおめでたい出来事よりも、この「京都駅跨線橋転倒事故」の方が余程強い印象があったのだろうし
- また、この「冬の記憶(9年1月)」が語られたと思われる(すずが亡くなった)21年1月から22年にかけては、プラカード事件に象徴される様に、食糧難もあり天皇に対する感情は極めて悪かったので
周作も、祝賀ムードの街の様子を語る気にもなれなかったのかもしれない。
「ほんらいはアニの 役目でしたが」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p6)
周作は「オニイチャン」という発音でしか聞いていないので、すずが要一の事を「鬼いちゃん」と呼んでいるとは知らなかった。
なので周作は当然、他人の前だからすずは畏まって(正座するだけでなく)アニと呼ぶだろう、という前提でこの話「冬の記憶(9年1月)」を創作してしまった…
- 一見ごく自然な台詞に思えてしまうこれ(しかもすず初登場時の最初の台詞群の一つである)も、この物語「冬の記憶(9年1月)」の語り手が周作だろうと思わせる根拠の一つ。
- 「アニ」がカタカナだったり、「ほんらいは」がひらがななのも
- それこそ「ほんらいは」漢字なところ、意図的にそうしてあって
- それは「此処にヒントがありますよ」という作者からのメッセージなのであろう。
「われながら いい出来じゃ ……」
こうの史代(2008)『この世界の片隅に 上』双葉社. p13)
周作がこの話「冬の記憶(9年1月)」をどういう筋道で創作したのかというと
- 孤児の少女にすずとの馴れ初めを聞かれて、人間違いだったとはさすがに言えないから…
- 何か作り話をしなければと考えた周作は、彼が実際に出会った(この物語の主人公のすずではない)すずという名の少女との出会いの場面を思い起こしたのだが、その時
- その周りでヨーヨーが流行っていたことも思い出した。
- そのヨーヨーが流行っていた時に「京都駅跨線橋転倒事故」を聞かされたことを思い出した。
- あるいはその話を聞かされていた時に、脇でモガの径子(当時17歳か18歳)が遊んでいたのかもしれない。モガの間でもヨーヨーは流行っていたそうなので。
- その事故は夜の出来事だと聞かされていたので
- 「夜になるとその事故のようなえらいこと = 転倒」するというばけもんの設定にすれば
- ばけもんに攫われたおかげで、二人は出会い
- 夜のように黒い海苔を武器に、ばけもんを転倒させて脱出し、二人は別れた
- という話の流れにできて、上手く話が繋がりそうだ、と周作は思ったのだった(上記の通り綻びも多いが、急拵えにしては上出来なのかも)。
- 「夜になるとその事故のようなえらいこと = 転倒」するというばけもんの設定にすれば
だから「われながら いい出来じゃ ……」という台詞には、この話の流れが出来た時の周作の気持ちが反映されているのかもしれないな。
- そういえば、周作と創作、似ている様な気も…
「家族」とは何か
血のつながりが「家族」、と言えるのだろうか
リンは(恐らくは血のつながった)父親に売られている。酒代のかわりに。
血のつながりの有無は「家族」であるかどうかと関係あるのだろうか
要一とすみはキセノの連れ子、すずは十郎の連れ子。(それを気づかせる仕掛けでもある)千鶴子は昭和11年〜昭和18年のどこかで草津の森田家に迎えられたのだろう。
すずとすみは血がつながっていない。でもとても仲の良い姉妹であることに、異論を差し挟む読者は皆無だろう。血がつながっていようがいまいが「家族」だ。
「家族」であり続けるためには
「第44回 人待ちの街(21年1月)」で江波の浦野家にいた三兄妹は、やってきたすずを「スイマセン」「スイマセン」「スイマセン」と落胆をもってむかえた。人間違い(人待ち街 / ひとまちがい)だと。
だからすずは持っていた江波巻きを分け与えることもせずにその場を去った。三兄妹がそう望まなかったからだ。他方で孤児の少女はどうだったか。きっかけは江波巻きかもしれないが、家族であることを望み、それを態度で示した。だからすず(と周作)はそれに応えた。
それは彼女達だけ、21年1月の広島駅前だけの話ではない。
家族が家族であるためには、家族であることを互いに望み、かつ具体的な態度で示さなければ、示し続けなければ、家族で在り続けることはできないのだ。黙って何もしなければ、家族は家族ではいられなくなる。
- 以下の引用の出典で解説されている、社会学者の上野千鶴子が提唱したファミリー・アイデンティティ論も参照されたし。
「自分はこの人を家族だと思うと定義しても、この人が自分のことを家族と思ってくれなければ、家族としてのコミュニケーションは難しい」
(出典)「「家族」の基準って何?「家族」って誰のこと?【「家族」の境界線について考える】」

「大潮の頃(10年8月)」でも描かれる折々に仕込まれた家族や親族の行事といったものも、あるいはそういう機能を果たす役割も持たされているのかもしれない。人生の知恵として。
そのことに気づいて貰いたくて、あえて浦野家や森田家にこんなにも手の込んだ仕掛けを施したのだろう。
- 更新履歴
- 2022/04/24 – v1.0
- 2022/06/11 – v1.1(「『家族』とは何か」を追記)
- 2022/06/21 – v1.2(「あの人 ばけもん じゃった?」を追記)
- 2022/12/28 – v1.2.1(関係する投稿のリンク先を追加)
- 2023/02/03 – v1.3(「モモヒキのすそに 書いてあった!」を追記)
- 2023/05/14 – v1.4(「兄と妹におみやげを 買うて帰るのです……」に、「(浦野家の)事情を誰も周作に教えなかった」旨を追記)
- 2023/05/23 – v1.5(ファミリー・アイデンティティ論について追記)
- 2023/05/30 – v1.6(読み易さを改善した他、「わざわざすみが「行って参ります」と出掛けるのを待ってから、「おこづかい 好きに使え」とすずに5円札を渡している」旨を追記)
- 2023/08/06 – v1.6.1(誤字修正)
- 2023/11/29 – v1.7(「ほんらいはアニの 役目でしたが」を追記)
- 2023/12/05 – v1.8(「祝賀ムードではない理由」を追記)
- 2023/12/06 – v1.9(「われながら いい出来じゃ ……」を追記)
- 2024/01/19 – v1.10(「荷物を背負わされているすずの背後の海苔干し台」を追記)
- 2024/01/20 – v1.11(「地域によって違う海苔干し台の段数」を追記)
- 2024/02/28 – v1.12(「砂利が ちらばっ とろうが」を追記)

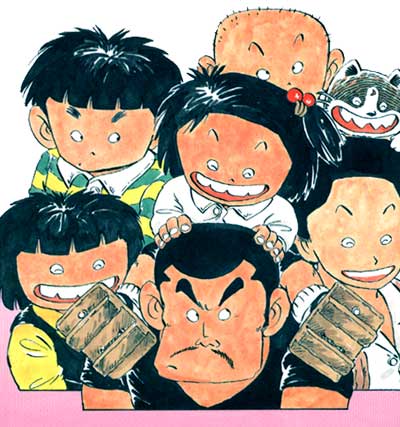

コメント