誰が、いつ、何を語って(かいて)いるのか
「此れは不幸の手紙ではありません」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p141)
人生相談の回(「第20回(19年11月)」)で触れたように、当時出回ったのは幸運の手紙であって、不幸の手紙は無かった。だからこのように断っているということは、この手紙は21年1月当時に語られた(かかれた)ものではない。
そしてその人生相談の回(「第20回(19年11月)」)の不幸(?)の手紙への回答では径子が
- 「知らぬ人から よくわからぬ事を 指図される事自体不幸である」と述べている。
不幸(の手紙)ではありません、ということなのだから、つまりこの「しあはせの手紙」は
- 「知っている人から(聞かされた) よくわかる事を 指図される事なく自ら」語って(かいて)いる
ものなのだ。
誰が、いつ、何を語って(かいて)いるのかは、この後で触れる。
「だってほら 真冬と云ふのに なまあたゝかい 風が吹いてゐる / 時をり海の匂ひも 運んで来る」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p141)
「海の匂ひ」はもちろん亡骸の匂い、「なまあたゝかい風」は腐敗による温度上昇が齎しているものだろうか。この「しあはせの手紙」が語られている目の前に、誰かの死体があるのかもしれない。
黒い人影はばけもんと同じく相生橋(「第44回 人待ちの街(21年1月)」p138)の相生橋と同じ傾きの欄干と柱がある)を渡って広島駅方面へ。多分孤児の少女。
「貴方などこの世界の ほんの切れっ端に すぎないのだから」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p146)
白い布で包まれた桐箱は「波のうさぎ」の水原哲の兄を連想させるが、あるいは「海の匂ひ」のもととなっている亡骸が漸く火葬されて桐箱に遺骨が納められたということだろうか。
(『この世界の片隅に』すずを見つける迄の)孤児の少女の居場所
「道では何かの破片が きらきら笑ふ」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p141)
道には髑髏が描かれている。原爆投下後の死体は衛生の観点からも兎に角焼かれては埋められていたので、ここに見えるのは一度埋められた死体が何らかのきっかけで地表に出てきてしまったものだろうか。
コマの枠線が他のコマと揃っていないので、多分ここから過去の様子に切り替わっている。新聞紙か何かを集めて次のページで布団代わりにしている。
左下のコマで、孤児の少女の母親の右手と海苔が大きく描かれている
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p142)
孤児の少女が見た、最後の普段の生活。「貴方の背を撫づる 太陽のてのひら / 貴方を抱く 海苔の宵闇」はそれらからの連想であろうか。
「貴方の背を撫づる 太陽のてのひら / 貴方を抱く 海苔の宵闇」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p142)
この2コマは同一の場所。「海苔の宵闇」では遠くに(孤児の少女の母親が最期を迎えた場所の脇にあった柱に似た)柱が見えるが、もしかすると、孤児の少女は自宅近辺から離れたくなくて、そこに寝泊まりしているのかもしれない。
- そうだとすると「第35回(20年7月)」p59)で
- 壕に寝てでも家の近くに居続ける誰かを見たすみの台詞「あそこは壕へ 寝とってじゃ」は
- 孤児の少女自身の体験と重なる。
- 詳細は下記「それが、語り継ぐ動機になる」で触れるが、彼女(孤児の少女)が語り継ぐにあたって
- 自身の体験を加味した、ということなのかもしれない。
- 孤児の少女自身の体験と重なる。
- 壕に寝てでも家の近くに居続ける誰かを見たすみの台詞「あそこは壕へ 寝とってじゃ」は
右手
孤児の少女の母親の右手だとすると
p142)「貴方の背を撫づる 太陽のてのひら / 貴方を抱く 海苔の宵闇」の「貴方」が孤児を指し、8月6日まで「右手」が「貴方」の背を撫で、抱いてきた代わりの「太陽のてのひら」「海苔の宵闇」であるとすれば、この「右手」はこの孤児の少女の母親の失われた右手ということなのだろうか。
他方で「右手」がはじめて読者に姿を見せるのはすずが右手を失ったすぐ後の「第33回(20年6月)」p42)で、20年6月だから、その時点では孤児の少女の母親の右手は失われておらず、その時点の「右手」の主が判らなくなってしまう。
もちろん、孤児の少女の母親はリンの過去も径子の経験も知らない。
すずの右手だとすると
リンの過去は「右手」がテルの紅で、孤児の少女が広島をさまよう描写は「右手」が鉛筆で描いている体裁だが、リンの過去も孤児の少女やその母親の経験も、すず(の右手)は知らない筈。
そして「右手」がはじめて読者に姿を見せるのはすずが右手を失ったすぐ後の「第33回(20年6月)」p42)だが、その時点ではすずの右手が失われたことが明確には描かれていない。現実を表す太い枠線のコマ内の「包帯を巻いたすずの腕」とすずの回想を表す細い枠線内に鉛筆書きする「右手」の位置関係は、すずの右手が(大火傷などはしていても)まだ原形を留めているかのように読者に思わせるものである。
右手についてすずが「昨日 ない事を思い知った」のは「第35回(20年7月)」p56)の20年7月であり、この「第33回(20年6月)」p42)の、右手が失われたことがすずの主観では認識されていない時点、かつ読者にもすずの右手がどういう状態か判らない時点で、初めて「右手」が姿を現すのは、「右手」が単純にすずの右手ではないことを伝える意図があると考えられる。「右手」がすずが失った手首だけでなく前腕部まで描かれていることも、この考えを補強する。
すずの右手ではないとすると…?
「ちょっとだけ、奇蹟が」に続く…
死ぬのは誰か
「留まっては 飛び去る正義 / どこにでも宿る愛」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p142)
似た表現の「第39回(20年8月)」p94)「この国から正義が飛び去ってゆく」の直後に太極旗を見て、それまで信じていた正義が暴力に過ぎないことにすずは気づいた。
恐らく国が勧めていたように、夫が戦死してなお賢母たらんと務めていたであろうこの孤児の少女の母親は、原子爆弾で全てを失って、その正義が単なる暴力の応酬に過ぎないことに気づいただろうか。
上段のコマで、左手で娘の手を引く母親
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p143)
「第33回(20年6月)」p38)左下のコマで、「右手に 風呂敷 / 左手に 晴美さん」と、もしそうであれば(すずは助からないが)晴美が助かった筈というすずの空想そのままに、母親の身体が盾代わりになって娘(孤児の少女)は助かるが、母親の命は尽きて、原子野のただ中に娘を一人取り残すことになる。
- 「母親の身体が盾代わり」と書いたが、それは母親の意思ではなくて、そうなったのは偶々に過ぎず「合理的な理由などない」。
- すずが生き残ったのに「合理的な理由などない」(「第43回 水鳥の青葉(20年12月)」参照のこと)のと同じように。
「そして / いつでも 用意さるゝ 貴方の居場所」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p143)
中段のこの2つのコマは、背景が繋がっていることから、母親が娘の手を引いて歩けたのはほんの数歩であることが判る。このような状態にあっても、母はがれきに腰掛ける時「いつでも 用意さるゝ 貴方の居場所」として左隣を空けている。
この5ヶ月後、新たな居場所としてすず(の右腕)が用意される。
そして「いつでも 用意さるゝ 貴方の居場所」は左隣だ。それは
- すずが(右手を失うとともに)右耳が聞こえなくなる(※「第42回 晴れそめの径(20年11月)」で説明済み)までは(周作から見ての)すずの居場所
- そして右耳が聞こえなくなってからは(すずから見ての)周作の居場所
でもある。つまりここでの「貴方」は(孤児の少女だけではなく)すずや周作も指している。
- そして下記の通り、すずも周作も死ぬのである。
「ごめんなさい / いま此れを読んだ 貴方は死にます」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p144)
生きる長さに長短はあるが、誰もが必ず死ぬ。そういう意味では間違っていない。晴美や孤児の少女の母親、「キンヤ」、読者だけではなく、すずも周作も。
ここでも、次のコマとコマの枠線が揃っていない。時間が切り替わっている。
何を「そびれ」たのか
「すゞめのおしゃべりを 聞きそびれ / たんぽゝの 綿毛を 浴びそびれ / 雲間のつくる 日だまりに 入りそびれ / 隣に眠る人の夢の中すら知りそびれ / 家の前の道すらすべては 踏みそびれ乍ら」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p144)
径子の膝の継ぎがなく(柄も「第5回(19年3月)」に晴美を連れて北條家に戻ってきた時のものと同じ。サンの寝間着の柄も同じ。)、円太郎はヘルメットをひっかけ、周作が一人で寝ていて、晴美がスカート姿で回覧板を回し、たんぽぽの綿毛が飛んでいる(概ね4〜6月頃)ことから、すずが里帰りしている「第6回(19年3月)」の数日の間。
という事はこれはすずが里帰りで見た「呉へお嫁に 行った夢 見とったわ !!」の夢の続き。翌日十郎に「買いそびれて」と言われたので、それが頭に残ったまま見た夢。
周作の広島電鉄への再就職(※後述のとおりであれば)を聞き、さらに復旧した453号を見かけたすずが、結婚後初めての里帰りで453号を見かけ、スケッチに夢中になって切符を「買いそびれ」浦野家でもう一泊した時の夢を思い出し、あるいは周作に話したのだろう。
「ものすごい速さで 次々に記憶となって ゆくきらめく日々を / 貴方は どうする事も出来ないで / 少しづゝ 少しづゝ小さくなり / だんゝに動かなくなり / 歯は欠け 目はうすく 耳は遠く / なのに其れを しあはせだと 微笑まれ乍ら」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p145)
一番その状況に年齢的に近いのはイトだが。晴美にはそうなる機会もなかった(しそびれた)ものでもある。
「皆が云ふのだから さうなのかも知れない / 或いは単にヒト事だから かも知れないな / 貴方などこの世界の ほんの切れっ端に すぎないのだから」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p146)
他人の桐箱を懐かしむ様子を描くことで、孤児の少女が8月6日から5ヶ月以上経過しても、8月6日の朝までの「ものすごい速さで 次々に記憶となって ゆくきらめく日々を」「どうする事も出来ないで」ただ抱え続けていたことを示している。
またそうなる機会のなかった(しそびれた)晴美にとってはヒト事。自分の身に降りかかる迄は他人の不幸もヒト事なのと同じように。
「家の前の道すらすべては 踏みそびれ乍ら」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p145)
晴美の周りにやや無理矢理な感じで竹が描かれているが。
- 晴美が突然すず(と読者)の前に現れて突然去っていったことを、かぐや姫のようだと連想させるためだろうか?
- そういえばかぐや姫が成長するのに要した期間は3ヶ月。すずが周作を忘れるのに要した期間と同じ。
- また、「第12回(19年7月)」で触れたように、竹は彼女の父「キンヤ」の名前の由来にも関わる。若くして亡くなった「キンヤ」もまた、晴美と同様に、上記のような機会はなかった(しそびれた)。
それが、語り継ぐ動機になる
「あんた… / よう広島で 生きとって くれんさったね」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p149)
「あんた…」のコマではまだすずは座っている。「よう広島で 生きとって くれんさったね」のコマではすずは立って(おそらくは歩きながら)孤児の少女の右手を握っている。孤児の少女の左手はすずの右腕を離さない。カラー頁の見開きでも最後のコマでも。
広島で生きていた孤児の少女は、広島で生きていた彼女の母親のことも、そしてこの後聞き出すのであろう晴美やすず自身のことも、(彼女達が亡くなった後も)語り継ぐことが出来る立場にある。あるいはそれこそが「居場所」の大切な意味なのかもしれない。
8月6日から5ヶ月を(物語上)必要としたのは、
- 周作との約束を果たすためには20年10月からさらに3ヶ月必要だったから。
- そして、3ヶ月必要な根拠は
- 「第20回(19年11月)」で触れたように、この物語『この世界の片隅に』は1946年1月に終える必要があるから。
- すず(や読者)にとっての晴美と同じように突然現れて去って行ったかぐや姫が成長に要した期間が3ヶ月であることに因んで。
- そして、3ヶ月必要な根拠は
- 孤児の少女が8月6日の朝までの「ものすごい速さで 次々に記憶となって ゆくきらめく日々を」長い長い間「どうする事も出来ないで」ただ抱え続けていることが、彼女が後にそれ(やすず達のこと)を語り継ぐ動機となり得るから。
- (単純に言えば、「しそびれた」感が日に日に高まっていく、ということ)
- 原爆投下後の体験を語る方々がそうであったように。
- (単純に言えば、「しそびれた」感が日に日に高まっていく、ということ)
『この世界の片隅に』連載時の実際の年の「平成」を「昭和」に読み替えると連載の年月に概ね一致するというよく知られた仕掛けは
- すずが体感した時間経過を読者も体感できる、という趣向であるが
- それは同時にこの語り継ぐ動機 =「しそびれた」感も同様に読者に体感して貰える、ということなのだろう。
- 加えて、この投稿の一番下の方で触れるが、この仕掛けには、さらに(特に読者である現代の我々にとって)重要な「真の意味」もあるのだ。
そこに巧みに導かれる孤児の少女
「しっ しっ」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p146)
吹き出しの背後で、前のコマで座っていた人がベンチを立ち去り、入れ替わりにすずが座ろうとしている。次のコマで転がる江波巻きは、片手でしか持てないすずが座ろうとしたはずみで落としたと思われる。そのため、そのベンチの裏側にあった桐箱に近づいてすぐ追い払われた孤児は、転がった江波巻きを拾うのに、そしてまた、すずの右腕を見つけるのに、丁度良い位置に導かれた形になる。
「しかも その貴方すら / 懐かしい切れゝの誰かや何かの 寄せ集めにすぎないのだから」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p146)
抱え続けていたきらめく日々、懐かしい切れゝの寄せ集めが、実際に目の前に、母親と同じように右手をなくした一人の女性、すずとして現れたように、孤児には思われたのだろう。
食べ物が、居場所に導く
中段左のコマで、転がった江波巻き
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p146)
「波のうさぎ(13年2月)」上巻p40)でお弁当として持たされているように、江波巻きは浦野家でよく作られていたのであろうし、浦野家同様海苔養殖をしている草津の森田家でも作るだろう一方で、周作の持ち物はp147)中段のコマや下段左のコマで開けようとしている水筒のようなもののようなので、この江波巻きは、周作ではなくすずが(草津の家を出るときに)持たされた筈。
ということは、江波の浦野家にいた三兄妹に分け与えることもできたはずだが、すずはそうしなかった。
上段右のコマで、すずは江波巻きを左手に持っている
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p147)
前のページで落とした江波巻きは既に諦めて拾おうとしていない。江波巻きを包んでいた竹の皮にはご飯粒が。
「ええよ 食べんさい」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p147)
地面を転がったのでおそらく砂まみれの筈。
「呉はうちの 選んだ居場所 ですけえ」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p148)
p147)右上のコマで竹の皮に付いていたご飯粒が、p147)左下のコマでは、すずの頬を居場所に選び、それを取って口にした孤児の少女はすずの右手を居場所に選んだ。すずは自分が「居場所」と口にした時に、孤児の少女がそうした振る舞いをしたので、孤児の少女が自分を居場所に選んだ、と感じ取ったのだろうか。江波の浦野家にいた三兄妹(やその他見かけたであろう多くの子供達)とは違って。
最後まで(そしてこれからも)重くのしかかる家父長制
「でも 遠うて 大変ですね」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p147)
「第44回 人待ちの街(21年1月)」p137)「上官の口ききで 再就職も何とか なりそうじゃ」という事で(あるいは21年1月8日に広島市に設置された復興局かもしれないが…)広島で見つかった仕事が、もし復旧した広島電気軌道(の453号)なら、20年9月に廃校になった広島電鉄家政女学校の生徒達の職を(とてもとても間接的にではあるが)奪った形にも思える。
- 広島電鉄家政女学校については、 さすらいのカナブン 氏の作品が以下のリンク先で読める。
「うちもこっちへ 通えます」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p148)
「通います」ではなくて。あくまで可能性。周作の許可があれば、ということ。
「その向こうが 広島よ」
「その向こうが 広島よ」「ありゃ? 寝んさったかね」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p150)
周作の九つの嶺の説明の合間にすずの発言がはさまっている。
三角兵舎が海苔の乾燥台のように並ぶ
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p151)
「第36回(20年7月)」p65)で広島へ帰ることを夢想したのと似た構図だが、すずは独りではないし、駆け出してもいない。
構図が似ているのは当然で、それは
- 海苔の乾燥台が並ぶ様子をすずが夢想した「第36回(20年7月)」p65)の場面は、実は
- 孤児の少女がこの時(21年1月)見た、この三角兵舎が海苔の乾燥台のように並ぶ場面をベースに、彼女(孤児の少女)が想像したものだから。
- そして「第36回(20年7月)」p66)「山を越えたら 広島じゃ」も、ここでのすずの台詞「その向こうが 広島よ」を踏まえている。
- ということで、このp66)「山を越えたら 広島じゃ」のコマのすずの左手には指が6本あるのだが、これは孤児の少女のちょっとした想像の誤りのようなもの、なのであろう(逆に言えば「第36回(20年7月)」が孤児の少女の想像であることの証かもしれない)。
- 孤児の少女がこの時(21年1月)見た、この三角兵舎が海苔の乾燥台のように並ぶ場面をベースに、彼女(孤児の少女)が想像したものだから。
- なお「第36回(20年7月)」では、当該回を(すずの気持ちを補った上で)語り継いでいるのが孤児の少女である旨説明済みである。
- 周作は走るのが遅すぎて(※「第39回(20年8月)」で説明済み)、走るすずの背中さえよく見えなかったので
- 彼女の背中の描写も出来なかったし
- 当然のことながらその時、海苔の乾燥台が並ぶ様子をすずが夢想したなどという洒落た脚色も出来なかったのだ…
- 周作は走るのが遅すぎて(※「第39回(20年8月)」で説明済み)、走るすずの背中さえよく見えなかったので
(カラー頁のお陰か)ちょっとだけ、奇蹟が
すずの右袖を掴んで離さない孤児の少女
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p151)
よく見ると、すずの右手が…あるような?
「今わたしに 出来るのは このくらゐだ / もう こんな時 爪を立てゝ / 誰の背中も掻いてやれないが / 時々は かうして 思い出して お呉れ / 草々」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p152)
「このくらゐだ」は、すず達と孤児の少女を引き合わせたことだろうか? それともシラミで痒みを引き起こしたことだろうか? あるいは前頁のすずの右手だろうか?
「かうして 思い出して」欲しがっている「わたし」が、亡くなった誰かだとすると、
- 要一(北條家ではすず以外は思い出せない)
- キセノ(すず以外はあまり思い出せない)
- 十郎(すず以外はあまり思い出せない)
- 孤児の少女の母親(孤児の少女以外は思い出せない)
- 晴美
のうちの誰なのか?
これらの登場人物のうちの誰かだとすると、論理的には(また「晴美の服じゃ 小まいかねぇ…」という台詞の隣に「かうして」とあることからも)晴美しかいない。そういえば、郵便配達人も晴美と同じく左利きだった。
そして晴美が「か(掻)いてやれない」代わりに「か(書 / 描)いて」いるのだ。その左利きの(ようにみえる)あの人が。
「右手」の正体、そして郵便配達人が左利きの(ようにみえる)理由については…
できればこのサイト「『この世界の片隅に』備忘録」を「冬の記憶(9年1月)」も含め一通りお読みいただいた上でどうぞ(右の下向き矢印をクリックすると読めます)。
- 「右手」だけが登場する場合、「か(書 / 描)いて」いる(右利きの)あの人は、直接自分の右手を見ながらそのまま模写しているので、そのまま「右手」として描かれている。
- 郵便配達人のように全身が登場する場合、「か(書 / 描)いて」いるあの人は、(自分の全身を直接は見れないから)鏡を見ながら模写しているので、左右が逆になり、左利きの(ようにみえる)人物として描かれている。
ということ。
- そして、「右手」がすずの頭を撫でる「第39回(20年8月)」以降最終回まで、この郵便配達人が登場する「第40回(20年9月)」以外全て「右手」が登場するのだが
- 「右手」がすずの頭を撫でるのは、右手の主からの「大変だったね、お疲れ様。この後の物語進行は任せて」といった意味合いで
- 「第40回(20年9月)」では、この後の物語の進行は任せておけとばかりに、右手の主が全身で登場しているので「右手」としては登場しないのだ。
- で、「第40回(20年9月)」の後、2回休載しているのは、この後の物語の進行は任せておけと張り切り過ぎて、台風の真っ只中に郵便配達してしまったから。
- (※中巻p111)「風邪ひかん 体質」ではなかったようで…)
- で、「第40回(20年9月)」の後、2回休載しているのは、この後の物語の進行は任せておけと張り切り過ぎて、台風の真っ只中に郵便配達してしまったから。
身も蓋もない話のように感じられるかもしれないが、この後の
- ‘(カラー頁にはなっても)「左手で描いた世界」のままなのは’
では、さらに身も蓋もない話をしなければならないので、その予行演習みたいなものだ。
- なお、この部分の結びは「草々」であるが、それと組み合わせて使われる「前略」で「しあはせの手紙」が始まっているわけではない。
- つまりこの部分(※おそらくカラーになってコマの枠線が極太になるカラー見開き頁の直前のコマから)は晴美によるものだが
- それ以外の部分は別の人が別の時に「か(書 / 描)いて」いる、ということになる。
- また、この「草々」は「葬送」との掛詞になっているから、その別の時というのは「葬送」の場面なのだろう。上記の通りすずも周作も死ぬのだから(しかも葬送に相応しく、それ以外の部分はカラー頁ではなくモノクロであるし)。
- ということは、この回の最後の部分がカラーなのは、その部分をカラーにしたかったからというよりも、それ以外の部分がモノクロであることを際立たせたかったから、なのだろう。
- つまりこの部分(※おそらくカラーになってコマの枠線が極太になるカラー見開き頁の直前のコマから)は晴美によるものだが
「晴美の服じゃ 小まいかねえ…」
こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p152)
刈谷が息子の服を交換したのと対照的に、径子は晴美の服を物々交換に出していなかった。形見という意味合いもあろうが、元々自分が着ていた服(※「第9回(19年5月)」で説明済み)でもあり、あるいはすずと周作にいずれ子供が生まれたら着てもらおうという心遣いがあったのかもしれない。
そして、この台詞が敢えて孤児の少女から離れた隅っこの場所に置かれているのは、
- 孤児の少女は晴美の身代わりなのだと誤解されないように
- そして晴美の身代わりなのだと安易に感動されないように
する為。そういう安易な感動を用意すると、そこで読者は思考停止してしまい、この物語『この世界の片隅に』の意図するところを自ら考えようとしなくなるから。
(カラー頁にはなっても)「左手で描いた世界」のままなのは
読者の世界もまた「左手で描いた世界」
「第35回(20年7月)」から続く「左手で描いた世界」。それは、裏の(真の)意味を別の言葉で言い換えている(タブーを言語化できない)ことによる精神的抑圧の現れであった。
- そしてそれは、孤児の少女を連れ帰ったからといって(当然)解消されるわけではない。
そして、物語の最後まで「左手で描いた世界」が続いたまま解消されないのは、物語が終わった後の、読者の住むこの現実世界もまた「左手で描いた世界」であって、それも家父長制同様、「『鬼イチャン』作/浦野すず」で描かれたとおり現代に続いている、ということを表現しているのだ。
- だとすれば
- 読者の住むこの現実世界で、とりわけ晴美とすずの右手を奪った米軍との関係では、何を別の言葉で言い換えている(タブーを言語化できない)のだろうか。
大西洋憲章
第二次世界大戦で米国が連合国側に参戦する前の1941年8月14日、チャーチルとルーズベルトによる会談で発表された大西洋憲章。両国が希望する戦後の形が書かれていて、その第8項には「世界の全ての国民の武力行使の放棄」と「脅威を与える / 与えそうな国の武装解除」が謳われているが、それ(つまり世界の安全保障)が達成されるまで誰がそれを担うのかというと、この憲章を発表した米国と英国が中心となって、なのである。
ダンバートン = オークス会議から国際連合憲章へ
1944年に開催されたダンバートン = オークス会議では、これが米・英・ソ・中が担う形に「進化」し、これを元に国際連合憲章が起草されるのであるが、ここでいきなり1つ目の「言い換え」がなされている。
- それは、第二次世界大戦で日本を敵国として戦った「連合国」と、この国際連合憲章の下で設立された「国際連合」はどちらも「United Nations」なのである。
- 上記国際連合憲章(和文)で「国際連合」ではなく「連合国」と訳されている箇所(5箇所)について、United Nations Charter(英文)を参照すると、勿論「United Nations」となっている。
何故同じ名前に別の訳語を当て嵌めたのか。そこには日本が見たくない裏の(真の)意味があるのであろう。
日本国憲法前文 – 平和を愛する諸国民?
1946年に公布された日本国憲法は、その前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という不思議な言い回しが挿入されているが、前述の「大西洋憲章」第8項にも同じ「平和を愛する諸国民」という言葉があり、これは当時の連合国 = 戦勝国と同義であるから、これはつまり
- 「日本の安全と生存は、戦勝国に委ねます」という意味である。
- ここに2つ目の「言い換え」がなされている。
日本の誰もが「自分を戦勝国の好きにして下さい」などとは思っていないだろう。しかし書いてあるのだ。すぐにはそれとわからないように言い換えて。
日本国憲法第9条 – その前提は実現していない
そして日本国憲法第9条第1項で「武力行使の放棄」、第2項で「戦力不保持・交戦権否認」を謳っているが、これも、米・英・ソ・中が世界の安全保障を担い、他の国は国際連合憲章第43条で想定されるいわゆる国連軍に兵力その他の便益を提供するという「大西洋憲章」から引き継がれた枠組みが前提となっている。しかしこんな大国の身勝手な枠組みに他国が乗る筈もなく、第43条に基づく国連軍というものは出来ていない。日本国憲法の前提は実現していないのである。
朝鮮戦争からずっと
そうこうしているうちに1950年6月朝鮮戦争が勃発し、油断していた米軍は当初劣勢に立たされるが、日本からの大量の軍事支援の継続によりどうにか持ち堪える。
- 他方いつまでも日本を占領しているわけにはいかないので独立させなければならない
- (ダグラス・マッカーサーは大統領を目指していたが、軍人のままでは立候補できないこともあり…)
- が、この軍事支援が途絶えれば戦争が継続できない。
そこで上記の(実現していない)国連軍を米軍に置き換えて、引き続き日本が独立した後も米軍を軍事支援するようにしたのが、いわゆる旧日米安保条約と日米行政協定の内容であった。
- 加えて朝鮮戦争で米軍が留守中の在日米軍基地を防衛する等を目的に、朝鮮戦争勃発から2か月も経たない1950年8月、警察予備隊が創設された。
- これについては、例えば「第211回国会 参議院 予算委員会 第3号 令和5年3月2日」でも、こういう答弁がなされている。
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121115261X00320230302/440
御指摘の文書の正式な和訳は存在いたしませんけれども、御指摘の箇所の和文仮訳をお示しするとすれば、次のとおりとなります。
日本区域において敵対行為又は敵対行為の急迫した脅威が生じたと合衆国政府が判断した場合には、警察予備隊及びその他全ての日本国の武装した組織は、合衆国政府が日本国政府と協議した後に指定する最高司令官の統一の指揮の下に置かれるものとするでございます。
この旧日米安保条約( + 日米行政協定)や警察予備隊は、ご存じの通り、見かけだけは変えられたものの実質的には同じ内容で今日まで引き継がれている。
つまり国連軍ではなく米軍に兵力その他の便益を提供する目的で現在の日本は存在している(少なくとも法的な枠組みの上では)。そういう意味では、戦前の日本の軍部が、戦後は(当初国連軍の想定であったが、結果的に)米軍に置き換わっただけ、ということなのだろう。
- なお、マッカーサーは(大統領を目指していたこともあり)元々米軍駐留を続けるつもりはなかったようだが
- 共産主義の中国の成立に加え朝鮮戦争勃発でそういうわけにはいかなくなり
- 他方で大西洋憲章で領土不拡大を謳っている手前、日本を独立( = 軍事支援が期待できない)させなければならない。
- 困ったマッカーサーにこのとんでもない屁理屈(国連軍 = 米軍。即ち日本による全面的軍事支援獲得)を囁いたとされるのがあのジョン・フォスター・ダレス。
- 彼は弟のアレン(CIA長官)とともに、彼らが関係する多国籍企業の利権保護のためにグアテマラの政府を転覆するという、その後、実現は難しいと思われたミルトン・フリードマンの新自由主義( = 既存の社会を暴力的 or 実際の暴力で破壊した後、多国籍企業が暴利を貪る仕組み)の現実化(以降、世界中に拡大して現在に至る)に必要な要素の一つを作った張本人でもある。利権獲得が原動力という点では誠に一貫しているが。
3つ目の「言い換え」
日本の誰もが「米軍の為に日本が兵力その他の便益を提供する」などとは思っていないだろう。
- しかし日米安保条約にはどこにも米軍が日本を防衛するなどとは書いていない一方で
- 米軍は(訓練でも出撃でも)日本のどこでも自由に利用できる上
- 戦争のような事態が生じた場合の指揮権は米軍にあるのだ
- (いわゆる指揮権密約であるが、それ(密約)以前に、そもそも日米安保条約第5条には「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動する」とある。
- 日本国憲法第9条で日本は武力行使を放棄し交戦権も否認しているのだから指揮権も何も成立する筈がなく、普通に考えれば、ここでいう「行動」が実質的に可能なのは米軍だけ。指揮権が米軍にあるのは当然なのだろう)。
- 念の為付言しておけば、どこかの政党が改憲案をぶち上げて支持者固めに余念がないようだが、随分と威勢の良い内容のように見えて、その実どこにも「指揮権を米軍に渡してはいけない」とは書いていない(し、米軍との現状を追認できるよう巧妙に工夫されているようにも見える)ので、米軍との異常な関係が見直されるとは考えられず、従って日本が下で述べる「戦争をする権利」だけでなく「戦争をしない権利」をも放棄しているという異常な現状が変わることもない、否、より完成形に近づけられるだけだと思われる。
- 日本国憲法第9条で日本は武力行使を放棄し交戦権も否認しているのだから指揮権も何も成立する筈がなく、普通に考えれば、ここでいう「行動」が実質的に可能なのは米軍だけ。指揮権が米軍にあるのは当然なのだろう)。
- (いわゆる指揮権密約であるが、それ(密約)以前に、そもそも日米安保条約第5条には「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動する」とある。
しかし外務省の「日米安全保障条約(主要規定の解説)」なるページには「第5条は、米国の対日防衛義務を定めており」という驚愕の説明が堂々と書かれている。一体どういう屁理屈をこねてそうなっているのか。あるいはそれさえもないのか。
- ここに3つ目の「言い換え」がなされている。
- 日本が自らを騙す為そうしているのかもしれないが
- 「言い換え」と見做すのにも無理のある出鱈目ぶりである。
戦争に巻き込まれていないということに「合理的な理由などない」
(この話のきっかけである朝鮮戦争勃発は、日本を武装解除し日本国憲法を制定させてから5年も経っていない時なのだから)考えてみれば当然で、
- 第二次世界大戦で多大な犠牲を払って占領した日本での権益を米軍が手放す筈がないし
- (日本が自分で指揮できる形の)再軍備を米軍が認める筈もない。
- ましてやその日本を防衛する謂れは米軍には全くない。
もともと武力行使を放棄しているのだからそれでもいいではないかと思われるかもしれない。
- しかしそこには落とし穴がある。
- 日本から米軍が出撃し、指揮権も米軍にあるということは、日本が戦争をするかしないかを決めるのは米軍だ、ということである。
- つまり日本は「戦争をする権利」だけでなく「戦争をしない権利」も放棄してしまっているのだ。
だから
- 日本が1945年以降「一見」戦争に巻き込まれていないのは偶々に過ぎず「合理的な理由などない」。
- すずが生き残ったのに「合理的な理由などない」(「第43回 水鳥の青葉(20年12月)」参照のこと)のと同じように。
- しかも、すずが生き残ったのに「合理的な理由などない」ことが描かれた(「第43回 水鳥の青葉(20年12月)」の話数は、上記のカラクリの源の一つである国連軍について定めた国際連合憲章の条文番号43と一致しているのだ。偶然だろうか。
- そして、すずはこの物語の後どうなったか(「冬の記憶(9年1月)」参照のこと)。
- すずが生き残ったのに「合理的な理由などない」(「第43回 水鳥の青葉(20年12月)」参照のこと)のと同じように。
「左手で描いた世界」の真の意味(意義、あるいは必要とされる理由)
日本の誰もが薄々気づいていながら、自らを騙す為なのか、その裏の(真の)意味を別の言葉で言い換えている(タブーを言語化できない)。これはすずの「左手で描いた世界」と同じなのであって、しかもそれは「『鬼イチャン』作/浦野すず」で描かれた家父長制同様、現代に続いているのだ。
- 「第15回(19年9月)」ですずは「夢から覚める とでも思うん じゃろか」と言ったけれども、薄々気づいていながら、自らを騙す為だなんて、まるで夢から覚めるのを拒むかのようだ。
上記の隠された問題( = タブー)をどのように捉えるとしても、
- 読者である我々はまず、そういうタブーを言語化出来ないという精神的抑圧の下にあるのだと気づかなかれば、そもそも問題を考えることさえできない。
- このような深刻な状態にあって、平静(平成)でいられないのは当然のこと。
- この作品が平成(平静)を昭和に言い換えつつ現代(昭和18年〜昭和21年←→平成18年〜平成21年)に描かれた真の意味(意義、あるいは必要とされる理由)はそこにあるのだろう。
- (※平成(平静)でいられないから昭和に言い換えて物語を紡いだ、ということ。)
- この作品が平成(平静)を昭和に言い換えつつ現代(昭和18年〜昭和21年←→平成18年〜平成21年)に描かれた真の意味(意義、あるいは必要とされる理由)はそこにあるのだろう。
- 更新履歴
- 2022/05/09 – v1.0
- 2022/05/17 – v1.1(「語り継ぐ動機」と、連載時の実際の年の「平成」を「昭和」に読み替えると連載の年月に概ね一致するというよく知られた仕掛けとの関係を追記)
- 2022/06/11 – v1.1.1(「こうのの日々」の記事「5月の新装版」をリブログ)
- 2022/06/13 – v1.1.2(「第23回(20年正月)」へのリンクを追加)
- 2022/12/06 – v1.2(すずが孤児の少女と出会うまで20年10月からさらに3ヶ月必要だった理由と、「晴美の服じゃ 小まいかねえ…」という台詞が隅っこの場所に置かれている理由を追記)
- 2023/03/13 – v1.2.1(「『鬼イチャン』作/浦野すず」へ戻るリンクを追加)
- 2023/06/03 – v1.2.2(江波の浦野家にいた三兄妹と孤児の少女の違いについて「冬の記憶(9年1月)」へのリンクを、広島電鉄家政女学校について さすらいのカナブン 氏の作品「原爆に遭った少女の話」へのリンクをそれぞれ追加)
- 2023/06/05 – v1.3(「(カラー頁にはなっても)「左手で描いた世界」のままなのは」を追記)
- 2023/06/07 – v1.3.1( “3つ目の「言い換え」” に「念の為付言〜」を追記)
- 2023/06/08 – v1.3.2(「United Nations Charter(英文)」へのリンクを追加)
- 2023/06/13 – v1.4(「第43回 水鳥の青葉(20年12月)」の話数が、国連軍について定めた国際連合憲章の条文番号43と一致している旨追記。)
- 2023/06/22 – v1.5(「ジョン・フォスター・ダレス」について追記)
- 2023/08/04 – v1.6(「しあはせの手紙」が「知っている人から(聞かされた) よくわかる事を 指図される事なく自ら」語って(かいて)いるものであること、「いつでも 用意さるゝ 貴方の居場所」の「貴方」がすずや周作も指していること、「三角兵舎が海苔の乾燥台のように並ぶ構図」が「第36回(20年7月)」p65)で広島へ帰ることを夢想したのと似た構図である理由、「草々」が指し示す意味を追記)
- 2023/08/15 – v1.7(「すずは独りではない」を、内容に沿った「その向こうが 広島よ」に変更し、p66)「山を越えたら 広島じゃ」のコマのすずの左手に指が6本ある理由を追記)
- 2023/08/27 – v1.8(「第15回(19年9月)」へのリンクを追加し、”まるで夢から覚めるのを拒むかのよう” である旨追記)
- 2024/03/31 – v1.9(一つ目の小見出しを「誰が、いつ、何を語って(かいて)いるのか」に改訂し本文中でも触れるとともに、「貴方の背を撫づる 太陽のてのひら / 貴方を抱く 海苔の宵闇」とすみの台詞「あそこは壕へ 寝とってじゃ」の関係を追記)
- 2024/04/05 – v1.10(8月6日についてのリンクを追加し、警察予備隊についての国会答弁を追記)
- 2024/04/05 – v1.11(「右手」の正体、そして郵便配達人が左利きの(ようにみえる)理由を追記)
- 2024/04/08 – v1.12(「第40回(20年9月)」に「右手」が登場しない理由を追記)
- 2024/04/09 – v1.12.1( ‘右手の主’ にリンクを追加)
- 2024/04/10 – v1.13(「家の前の道すらすべては 踏みそびれ乍ら」の位置を変更し、晴美の父「キンヤ」との関連を追記)
- 2024/04/12 – v1.14(「母親の身体が盾代わり」となったのは母親の意思ではなくて、偶々に過ぎず「合理的な理由などない」旨追記)

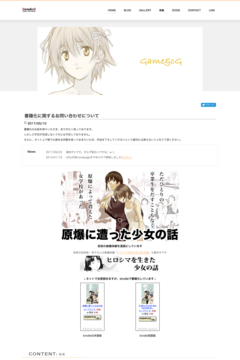

コメント